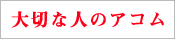第33回 マウンド上の悔し涙 〜1999,October〜
マウンド上で涙をこぼしながら投げたのは後にも先にも上原浩治ひとりではないだろうか。
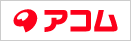
1999年10月5日、神宮球場。ヤクルト対巨人戦。7回1死無走者の場面だ。得点は5−0で巨人5点のリード。マウンド上には巨人のルーキー上原。打席にはヤクルトの4番ロベルト・ペタジーニ。
ここでキャッチャー村田善則は敬遠の指示。ところが、上原は納得がいかない表情を浮かべる。最終的に敬遠したものの、マウンドの土を蹴り上げ、ロージンバッグをたたきつけた。そしてこぼれる涙をユニホームの袖でぬぐった。
上原が敬遠を嫌がったのは当然だ。僅少差のゲームならともかく、5点もリードがあるのだ。さらにペタジーニとは、この対戦まで14打数0安打、6三振と完璧にカモにしていた。「敬遠? それはしゃべりたくありません。経験? そりゃありますよ。でもやっていい敬遠と……」。そう言って次に続く言葉を飲み込んだ。
ではなぜ巨人ベンチは敬遠を指示したのか。ペタジーニは4番の松井秀喜と熾烈なホームラン争いを演じていた。いくら上原がペタジーニをカモにしているとはいえ、一発が飛び出せば、松井の逆転ホームラン王の可能性がきわめて低くなる。長嶋茂雄監督(当時)は「松井だって中途半端な攻め方をされた」と6回の四球を指摘し、その報復行為だったことをほのめかせた。
今でも覚えているのは、ペタジーニに投じた敬遠のボールがすさまじく速かったこと。あれはベンチへの無言の抗議であると同時に、ピッチャーとしてのなけなしの誇りだったに違いない。
「僕は野球を楽しんでやりたいものですから」
ピッチャー上原浩治の原点がそこにある。

※二宮清純が出演するニッポン放送「アコムスポーツスピリッツ」(日曜17:30〜18:30)好評放送中!
>>番組HPはこちら
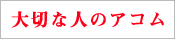
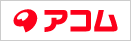
1999年10月5日、神宮球場。ヤクルト対巨人戦。7回1死無走者の場面だ。得点は5−0で巨人5点のリード。マウンド上には巨人のルーキー上原。打席にはヤクルトの4番ロベルト・ペタジーニ。
ここでキャッチャー村田善則は敬遠の指示。ところが、上原は納得がいかない表情を浮かべる。最終的に敬遠したものの、マウンドの土を蹴り上げ、ロージンバッグをたたきつけた。そしてこぼれる涙をユニホームの袖でぬぐった。
上原が敬遠を嫌がったのは当然だ。僅少差のゲームならともかく、5点もリードがあるのだ。さらにペタジーニとは、この対戦まで14打数0安打、6三振と完璧にカモにしていた。「敬遠? それはしゃべりたくありません。経験? そりゃありますよ。でもやっていい敬遠と……」。そう言って次に続く言葉を飲み込んだ。
ではなぜ巨人ベンチは敬遠を指示したのか。ペタジーニは4番の松井秀喜と熾烈なホームラン争いを演じていた。いくら上原がペタジーニをカモにしているとはいえ、一発が飛び出せば、松井の逆転ホームラン王の可能性がきわめて低くなる。長嶋茂雄監督(当時)は「松井だって中途半端な攻め方をされた」と6回の四球を指摘し、その報復行為だったことをほのめかせた。
今でも覚えているのは、ペタジーニに投じた敬遠のボールがすさまじく速かったこと。あれはベンチへの無言の抗議であると同時に、ピッチャーとしてのなけなしの誇りだったに違いない。
「僕は野球を楽しんでやりたいものですから」
ピッチャー上原浩治の原点がそこにある。

※二宮清純が出演するニッポン放送「アコムスポーツスピリッツ」(日曜17:30〜18:30)好評放送中!
>>番組HPはこちら