中国はさすがに統制国家である。国民には法令順守の精神が叩き込まれている。それが証拠に救急車までが信号を守るのだ。

マラソンの取材は地下鉄を乗り継ぐに限る。17日の女子マラソン、10キロ、25キロ、35キロ、そしてスタジアムで観戦する計画を立てた。16キロあたりから土佐礼子が遅れ始めたとの連絡を受けた。
そして25キロ地点、私の目の前で木内敏夫コーチが抱きかかえるようにして土佐を止めた。大変だったのはここからだ。すぐに係員が駆けつけるのかと思ったら誰も来ない。土佐は大通りの脇に放置された。
不幸中の幸いは、たまたま25キロ地点で土佐の高校時代の恩師・竹本英利氏と高校、大学時代の同級生が応援していたこと。竹本氏らが土佐を抱きかかえながら木陰に連れて行った。
土佐は嗚咽をもらすだけで何も語れない。体は小刻みに震えている。「礼子、もう終わったのよ」「大丈夫よ、何も心配することはないのよ」。女性の同級生が耳元で声を枯らすが、何の反応もない。
大げさではなく最悪の事態が脳裡に浮かんだ。もう取材どころではない。閉まっていたビルを開けさせ、数人がかりで土佐を運んだ。ビルの関係者が簡易ベッドを提供してくれた。水を勧めても全く口にできない。ただ嗚咽をもらすだけ。時折、体がピクピクと震える。
待てど暮らせど救急車はやって来ない。「救急車はまだか?」。日本語も英語も通じない。我々の苛立ちを察知した路上の中国人がはるか遠くの救急車を指差した。
私は愕然とした。あろうことか救急車は、はるか先で信号待ちをしていたのだ。五輪ゆえの交通規制はあるだろう。しかし、ここで信号待ちかよ。
ご主人の村井啓一さんが土佐を背中におぶって歩道を走った。かなりの距離があった。途中から“バケツリレー”のようなかたちで交代で土佐を運んだ。あまりの軽さにびっくりした。ここまで身を削ってレースに臨んでいたとは…。言葉は悪いがミイラのようだった。
同郷ということもあって土佐を取材し始めて9年になる。まさかこんな壮絶なエピローグが待ち受けていようとは…。もう充分だ。愛媛に帰ろう。早く北京を出よう。
<この原稿は08年8月20日付『スポーツニッポン』に掲載されています>
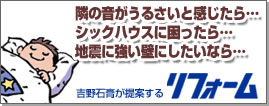 ◎バックナンバーはこちらから
◎バックナンバーはこちらから