西本恵「カープの考古学」第76回<カープ再び危機――長谷川引き抜き事件その8/広島ファンのすべてを背負った森田よし子>
昭和27年3月、カープは3年目の開幕を前に、絶体絶命の危機に立たされていた。名古屋軍がエースの長谷川良平を引き抜こうとかくまったため、帰省先の名古屋から広島に戻っていなかったのだ。その危機の中、長谷川を連れ戻そうと、長谷川が広島の母と慕う、飲み屋カザリン経営者の森田よし子が立ち上がった。敵陣名古屋まで一人で乗り込んでいくのだ。ところが、そうやすやすと名古屋軍の幹部が長谷川を森田に会わせるはずはなかった。
「広島の母」の出番
長谷川はカープ宿舎御幸荘に籍を置きながらも、人と徒党を組むのは性分にあわないとばかり、カザリンの2階に寝泊まりすることも多かった。長谷川にとっては、名古屋に住む実の母親は当然ながら大事にした。だが、森田を「広島の母」と呼び、母親同然のように大切にしていたのだ。その森田が名古屋まで来てくれるとあらば、心躍り、長谷川は会いたいとばかり子どものようにダダをこねるのであった。
<「『森田さんに会えないのならオレは死ぬる』と長谷川が強気に出たのでようやくはじめて広島側の人と会うことができたのである」>(「中国新聞」広島カープ十年史61回・昭和35年1月29日)
長谷川が森田に会うことができたのは、名古屋駅のホームであった。この肝っ玉女将と呼ばれる、森田のスクランブル出動により事態は少しずつ好転していく。ただ、駅で出会ったのは、名古屋軍関係者5、6人が影から見守っていた中でのこと。名古屋軍としては手綱を緩めたわけではなかった。
カープ球団のみならず、広島県民、市民すべての期待を背負った森田。その森田からの名古屋へ行くんじゃない、という言葉は長谷川に響いた——。
<「行くんやないのよ。あなたの将来は私に任せなさい」>(『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子・宝島社)
長谷川は、例年ならばキャンプ練習をするはずだったが、一切ボールを握っておらず、ほとほと疲れ果てており、顔色には精彩を欠いており青白かった。
<名古屋市内の旅館から伊東へ、伊東から東京へと転々とし、広島の使者から巧みに逃げ回る>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)
長谷川は憔悴しきっていた。寄りかかれるものがあれば、すがりたかった。
<「森田のおばさんに全てを任せよう」>(『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子・宝島社)
長谷川の心はこの時決まった。森田は、名古屋軍の球団幹部らと、名古屋駅近くの料亭で一戦を交えることになった。
<中村ら八人が森田に激しい言葉を浴びせる>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)
これにたじろぐことなく森田はじっと耐えて聞いた。さらに名古屋軍は長谷川の母親のことを盾に追い打ちをかける。
心は広島に
<「名古屋だったら、お母さんもいるじゃないか」>(『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子・宝島社)
痛い所をついてくる名古屋軍。さらに<「なぜ月給が少なく、酷使される広島へ連れて帰るのか」>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)とカープのアキレス腱ともいえる親会社のない境遇をついてくる。しかし、森田も負けじと、これには反応した。
<「名古屋なら、杉下、近藤の次でしょ。広島ならエースです」>(同前)
名古屋軍には、かの杉下茂がいる。近藤貞雄もいる。しかし、カープで勝ち星が計算できるのは長谷川しかいない。名古屋軍の気持ちは揺れ始めた。カープにとってはかけがえのないエース。これは誰が聞いても周知の事実であった。単に投手陣の頭数に入れたいという名古屋軍の思惑を打ち破るかのような、森田の一言により、形勢は変わった。なにを言われても引かない森田のド根性に名古屋軍が折れる様相となった。この一連のやりとりの中で、当事者の長谷川は、森田の後ろで小さくなってしまったままであった。
<「長谷川に代わる選手を出すから譲ってくれ」>(「中国新聞」広島カープ十年史62回・昭和35年1月30日)と名古屋軍が食い下がる。森田にあっては長谷川の未来にも可能性を見出していた。
<「今年の長谷川は精神的にも参っているから、恐らくたいした働きもできないでしょう。それを連れて帰るのは、長い将来のことを思えばこそで、一年限りで譲るくらいなら、今年譲ってしまうでしょう。長谷川は五年でも、十年でも本人のやれる限り広島から離しません」>(同前)
長谷川のカープ復帰が決まった瞬間といえよう。中村三五郎代表以下、スカウトの小野稔ら、球団幹部からは声も出なくなった。3カ月あまり、長谷川を追いかけてきた中で、忸怩たる思いはあったろう。ただ、長谷川も黙ったままだった。
ところが、ここで球界において、人格者とされる名古屋軍の天知俊一監督が、下を向いたままの長谷川に口を開いた。
<「あんたが悪いんじゃないんだよ。みんな球団が悪いんじゃ。こうと決まったからには、私は広島へ行ってみなさんに謝る」>(『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子・宝島社)
憔悴しきった上に、しょげかえる長谷川。なにも考えられない放心状態であったろうか。グラウンドでの戦いはいかにメンタルが大事であるかを知る天知である。天知の言葉は、母のいる名古屋へ帰りたいと、揺れていた弱冠20歳の長谷川の気持ちをふっ切らせるもので、心を広島に向かわせた。
汽車に乗り込む長谷川
長谷川に迷いがなくなったわけではなかった。むしろ、心配事が増えてもいた。というのも、普段から熱烈な地元カープファンの声援は、ありがたい反面、恐ろしさもあった。カープ選手の全てに寛容であるわけではなかったからだ。些細なミス、いわゆるボーンヘッドなど、許されないプレーをしようものなら、すぐさま怒声が浴びせられる。このことは、長谷川はよくよく知っていた。
今回の騒動の、そもそもの発端は、名古屋軍の緻密な作戦によるものであるのは、間違いなかろう。そして、まんまと、その術中にはまってしまい、移籍問題へと発展したのだ。
<「ファンになんと言われるだろう」><「どんな仕打ちをされても仕方ないが…」>(共に『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)
長谷川の心中は穏やかでなかった。やつれきった長谷川の青い表情。この3カ月あまりの間、移籍問題で揺れ動いた疲労感と精神的な閉塞感で、なんともいえない列車での帰還となった。3月20日の下り急行「筑紫」に乗り込んだ長谷川の表情には、生気がなかった。
列車は中国地方に入っていた。
<列車が岡山に着いたとき、石本監督が乗り込んできた>(「読売新聞」カープ十年史『球』73回)
なんという気配りであろうか、長谷川の心中を察した上だろう。移籍問題のゴタゴタで疲弊した長谷川に配慮しての行動であった。
<「ハセ、よう帰ってきてくれたの。サア、いっしょに広島へ帰ろうや」>(同前)
実に石本秀一らしい出迎えだった。長谷川の心は穏やかになり、広島への気持ちが向いた。石本は、事前に新聞を通じて、長谷川が戻ってくるのなら、温かく迎えてやる旨のメッセージを発信していたこともあり、長谷川は石本の大きな気持ちによって、迎えられたのである。
少しばかり安堵した長谷川であった。あとは、広島駅に着いて、ゆっくり帰路につけばいい。ホームが見えてきた。なんだか騒がしい。何だろうか――。そして駅に着いた。
広島の地に足を踏み入れる長谷川。この時、彼は驚きの光景を目にする。次回、長谷川引き抜き事件編は、クライマックスを迎える。果たして長谷川を駅で待っていたものとは――。ご期待あれ。
【参考文献】
『カープ30年』冨沢佐一(中国新聞社)、「中国新聞」広島カープ十年史61回(昭和35年1月29日)、同62回(昭和35年1月30日)、『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子著・駒沢悟監修(宝島社)、「読売新聞」カープ十年史『球』73回
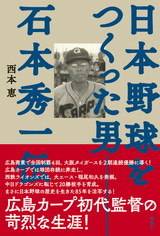 <西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>スポーツ・ノンフィクション・ライター
<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>スポーツ・ノンフィクション・ライター
1968年5月28日、山口県玖珂郡周東町(現・岩国市)生まれ。小学5年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活6年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話-じゃけえカープが好きなんよ」(2008年・トーク出版刊)は、「広島カープ物語」(トーク出版刊)で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男--石本秀一伝」(講談社)を上梓。2021年4月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり~異文化の観点から~」を研究。
(このコーナーのスポーツ・ノンフィクション・ライター西本恵さん回は、第3週木曜更新)
