「その話は墓場まで持っていこうと思っているんですよ」。真夏の広島市民球場の放送ブース。クールな表情が少しだけくもった。そこまで聞けばもう十分だった。それ以上、追及する気にはなれなかった。また追及したとしても何の意味もない。あえて言えばそれが勝負のあやというものだろう。
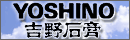
言葉の主は元広島監督の三村敏之さん。現役時代は好守巧打の内野手として活躍した。
1979年の日本シリーズは広島と近鉄の間で行われた。勝負は最終戦にまでもつれ込んだ。
舞台は大阪球場。9回裏、得点は4対3と広島1点のリード。マウンドには広島の絶対的な守護神・江夏豊が立っていた。
無死満塁。打席には山口哲治の代打・佐々木恭介。カウント1−1からのボールを叩いた。ワンバウンドで三塁線を襲う。サードに入っていた三村はジャンプして飛びついたが、わずかに打球は差し出したグラブの上を通過し、ファウルグラウンドに転がった。
三村が飛びついた地点はラインの内側であり、もし打球がグラブと接触したあとでファウルグラウンドに転がったのであれば、この一打はフェアである。打球の転がり方からして三塁ランナーはもちろん二塁ランナーも本塁を陥れていた可能性が高い。つまり佐々木の劇的な逆転タイムリーで近鉄がサヨナラ勝ちを収め、初優勝、闘将・西本幸雄、悲願の胴上げ――こうなっていたのである。
結局、3塁線の打球をファウルと判定された佐々木は2−2のカウントから江夏が投じた内角低めのカーブにタイミングが合わず、空振り三振に切って取られた。
なおも一死満塁。絶体絶命のピンチであることにかわりはない。ここで迎えたバッター石渡茂に、2球目、江夏はカーブの握りのまま外角にウエストボールを投じる。石渡の気配から江夏はスクイズのサインを見破ったのだ。三塁ランナーの藤瀬史朗が三本間でタッチアウト。局面は二死二、三塁にかわる。江夏はカウント2−0からヒザ元へカーブを投じると石渡のバットがクルリと回った。世にいう「江夏の21球」である。
名勝負の陰にドラマあり。「墓場まで持っていく」秘話も、それもまたひとつのドラマなのかもしれない。
<この原稿は07年10月31日付『スポーツニッポン』に掲載されています>
 ◎バックナンバーはこちらから
◎バックナンバーはこちらから