高木啓充(東京ヤクルトスワローズ/愛媛県松山市出身)最終回「先発で開幕1軍を!」
 「サイン、見えてんのか!?」
「サイン、見えてんのか!?」マウンドに歩み寄り、キャッチャーマスクをとった古田敦也は怒っていた。2006年4月12日、横浜スタジアムの横浜対東京ヤクルト。ルーキーピッチャーの高木は唇をかみしめながらベンチへ駆け足で退いた。何が何だかわからないうちに終わったプロ初登板だった。
この試合、ヤクルトは8−2と大きくリードしていた。ほぼ勝利が確実ともいえる最終回、1軍昇格を果たしていた高木に初めてチャンスが与えられたのだ。リードするのはプレーイングマネジャーの古田。バッテリーを組んだ経験はキャンプ中でもほとんどなかった。先頭の佐伯貴弘をセンターフライに打ち取ったものの、緊張で頭は真っ白。続く打者には四球を与えてしまう。さらに巧打者・種田仁に2塁打を浴びると、一発のある村田修一には再び四球。すべての塁が走者で埋まり、マスクをかぶった指揮官はピッチャーの交代を告げた。
結果が出なかったのは緊張のせいだけではない。何より、マスク越しの監督が出すサインがよく見えなかった。実はこれが高木にとって実戦では人生初のナイトゲーム。カクテル光線に照らされた中とはいえ、アマチュア時代のデーゲームとは大きく勝手が違った。首脳陣にメガネかコンタクトをつけるように指示され、ほどなくファームに落とされた。その後は夏場に再び昇格の機会を得たものの、先発で2回も持たず2失点。即戦力右腕とみられていただけに、ルーキーイヤーは期待を大きく裏切った。2年目の07年は結局、1度も1軍に上がれなかった。「上原さんを超える投手になりたい」と豪語していたプロ入り前の自信はガラガラと崩れ去った。
飛躍の陰に発想の転換
「1年、2年とやるにつれて、これはムリだなと思いましたね。ストライクが入らないし、球筋も変化球のキレも他の選手と比べたら劣っている。このままだと確実に通用しないなというのがありました」
その思いは焦りを生んだ。実力が伴わない状態で高望みしても好結果につながるはずがない。なかなか思うようなピッチングができず、悶々とした日々をファームで過ごした。
「プロに入って明らかに球速が落ちましたよね。“なんでや”と聞いたら、“アウトコースにコントロールよく放れと言われるから、思い切って投げられなくなった”と言っていましたね」
大阪体育大学時代の恩師、中野和彦監督は久々に会った教え子が悩んでいた姿を覚えている。
霧の中で暗中模索していた高木に、光が見えてきたのは3年目(08年)のシーズンだ。
「まずは自分のできる範囲のことをやらないと、どうしようもないと思ったんです。ピッチングだけじゃなく、バント処理にしろフィールディングにしろ、基本的なところでミスったら、僕のような何のとりえもないピッチャーは終わりですから」
高田繁監督が就任したこの年、ファームで安定した投球をみせ、交流戦期間中に2年ぶりの1軍マウンドを経験した。「必要以上に速い球を投げることを目指すのではなく、今、自分の能力内でできることを確実にこなすことを心がけました。意外と落ち着いて投げられましたね」。もう焦ってばかりいた過去の自分は、もうそこになかった。5試合に中継ぎ登板して、勝敗はつかず、防御率3.38。まずまずの結果を残したことが、4年目のブレイクにつながった。
三振をとろうとは思わない
2010年、高木にとって5年目のシーズンはルーキーイヤー以来の1軍スタートでキャンプインを迎える。昨季終盤に4勝をあげてチームのクライマックスシリーズ進出に貢献したことが評価され、年俸は800万円から1700万円に大幅アップした(金額は推定)。その分、周囲の期待は大きい。「でも、今年は大丈夫だろうという気持ちはまったくないですよ。そう思った時点でダメですよね」。昨季途中まではクビを覚悟していただけに、危機感は消えていない。
「僕は球が速くなくて、三振がとれない。中継ぎでは危ないから使えないです。それに三振を取ろうなんて、これっぽっちも考えていませんし……」
自分の持ち味が出せるのは先発だと感じている。テンポよく投げて、バックを信頼し、打たせて取る。少々ヒットは打たれても、要所は締め、最少失点で切り抜ける。「僕がなんとかできるのはそれくらいですから」。謙虚な言葉は、自らの生きる道を見つけた裏返しでもある。
ヤクルトは右の館山昌平、左の石川雅規に続く、第3、第4の先発の確立が上位を狙うための絶対条件だ。その座を争うのは高木の他に、由規、村中恭兵、増渕竜義ら若手に、実績のある川島亮、一場靖弘、戦力外から復活を遂げたユウキ、新外国人のトニー・バーネット……。チーム内の生存競争は激しい。
「実際に1軍で先発すると、コントロールの大事さを学びました。ちょっとでもコントロールを乱すと打たれてしまう。細かいコントロールや変化球のキレをあげていかないと甘くないですよ」
高校、大学時代はコントロールがアバウトなタイプだった。プロに入って最も変わったところは、本人も「制球に対する意識」と明かす。今も「高低、コースへの投げ分け」は課題のひとつだ。150キロの豪速球や絶対的な変化球のある投手なら、野球ゲームのように、とにかくそれを投げていれば相手を封じられる。だが、残念ながら現在の高木にそれはない。ならば直方体のストライクゾーンを活用し、2次元ではなく、3次元のピッチングをすることが求められている。
「とにかく(キャンプ中の)紅白戦で結果を出して生き残らないと。まずは開幕1軍ですね。そして1年間、ケガなく投げ抜くことです」
新年は故郷の松山で始動し、1月中旬にはチームの先輩である石井弘寿、相川亮二らとサイパンで自主トレに励んだ。大事なシーズンに向けての準備はほぼ整った。燕の救世主はチームの柱になりうるのか。その分岐点となるキャンプが2月1日、沖縄・浦添で幕を開ける。
(おわり)
>>第1回はこちら
>>第2回はこちら
>>第3回はこちら
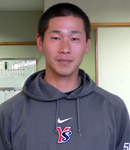 <高木啓充(たかぎ・ひろみつ)プロフィール>
<高木啓充(たかぎ・ひろみつ)プロフィール>1983年9月16日、愛媛県松山市出身。中学時代は砲丸投で四国大会3位の成績を持つ。宇和島東高では投手兼内野手として、阿部健太(現阪神)擁する松山商、越智大祐(現巨人)擁する新田などと甲子園行きを争う。全国大会出場はならなかったが、打撃でも高校通算30本塁打をマーク。大阪体育大に進学後、3年時(04年)に大学の先輩、上原浩治(現オリオールズ)以来のリーグ戦ノーヒットノーランを達成。4年時(05年)には33イニング連続無失点などを記録して“上原2世”として注目を集める。同年の大学・社会人ドラフトでヤクルトが4巡目で指名。1年目の開幕当初に1軍デビューを果たしながら、結果を残せず、プロ入り3年間は未勝利。4年目となった09年は8月に1軍昇格すると、9月16日の横浜戦に先発して初勝利。続く22日の広島戦で初完封勝利をおさめる。結局、12試合に登板して4勝(0敗)、防御率1.64の好成績を残し、チームのクライマックスシリーズ出場に貢献した。右投右打。身長181cm、85キロ。

(石田洋之)
